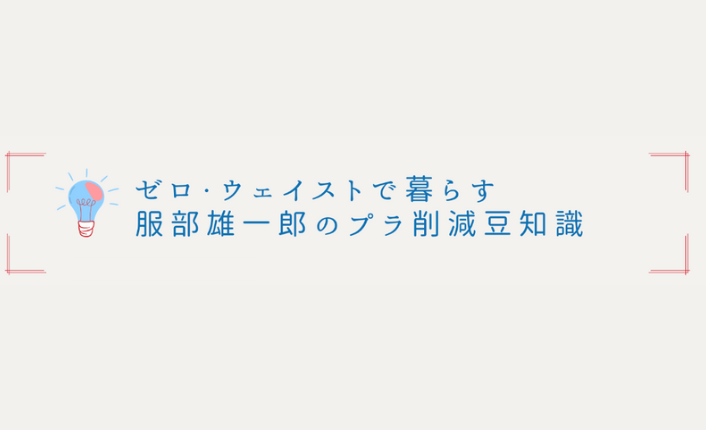
LEARNING CONTENTS
日々のエコアクション
第14回『プラの分別、再確認!』
とてもややこしい「容器包装プラスチック」
プラスチックの分別、「実はあやふや…」だったりしませんか?
日本はごみの分別が自治体によってまったく異なるため、戸惑う方も多いことと思います。
まず、いちばん一般的な「容器包装プラスチック」。これは様々な食品パッケージや、洗剤・シャンプーのボトルなどのプラスチックを分別して資源化するものです。あくまでも「容器包装」が対象なので、たとえばプラスチック製のおもちゃやハンガー、クリアファイル、CDやDVDなどは対象外となります。
「素材は同じプラスチック」なのに、なぜこんなにややこしいシステムなのかというと、20年ほど前に、国として「もっとリサイクルを進めていかなければ!」となった時、割合の多かった容器包装に狙いを定めて、事業者に費用負担して資源化を進めていくことになったため。
結果的に、容器包装以外のプラスチックごみは置き去りにされてしまったのです。
「燃えるごみ」や「燃えないごみ」となるプラスチックも…

容器包装以外のプラスチック(=いわゆる「製品プラ」)は、多くの自治体で「燃えるごみ」もしくは「燃えないごみ」に分別することとされています。焼却炉の性能などにより、まったく同じものが「燃える」とされたり、「燃えない」とされたりするので、これまたややこしい部分です。 さらに、「容器包装プラスチック」についても、コストや労力に見合わないなどの理由で分別資源化を行わず、「すべて燃えるごみ」として処理している自治体もあります。
この辺りは自治体ごとにルールを確認してみるよりほかないので、疑問に思った方はぜひお住まいの自治体のウェブサイトを覗いてみてください。ほとんどの自治体が情報をわかりやすくまとめてくれています。
解決の流れも生まれている
こうしたややこしい現状にはかねてより批判も多く、ついに令和4年の法律改正(通称「プラ新法」)で、容器包装プラスチックも製品プラスチックも「すべてまとめて一元的に資源化しましょう」という指針が示されました。
残念ながら「努力義務」のため、対応している自治体はまだごく一部ですが、これが広がっていけば、仕組みはかなりわかりやすくなるはずです。
次回は容器包装プラスチックの分別のコツや注意点を紹介します。
その他の記事
日々のエコアクション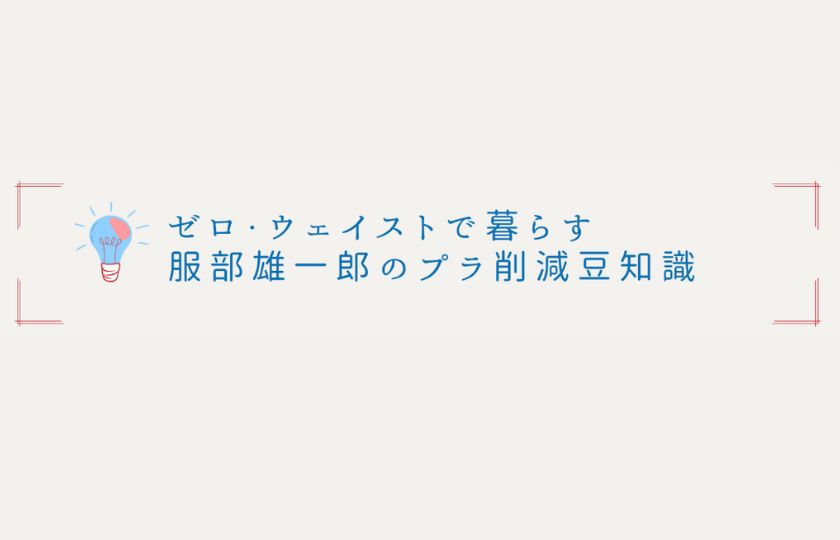
第17回『プラスチックは体に悪い!?』
プラスチックを「食べている」?? 数年前、「人は1週間にクレジットカード1枚分のマイクロプラスチックを食べている」という研究結果が広く報道され、社会に衝撃を与えました。 この数字は「さすがに盛りすぎだった」とも言われ、実...
記事を読む
取り組み事例(その他)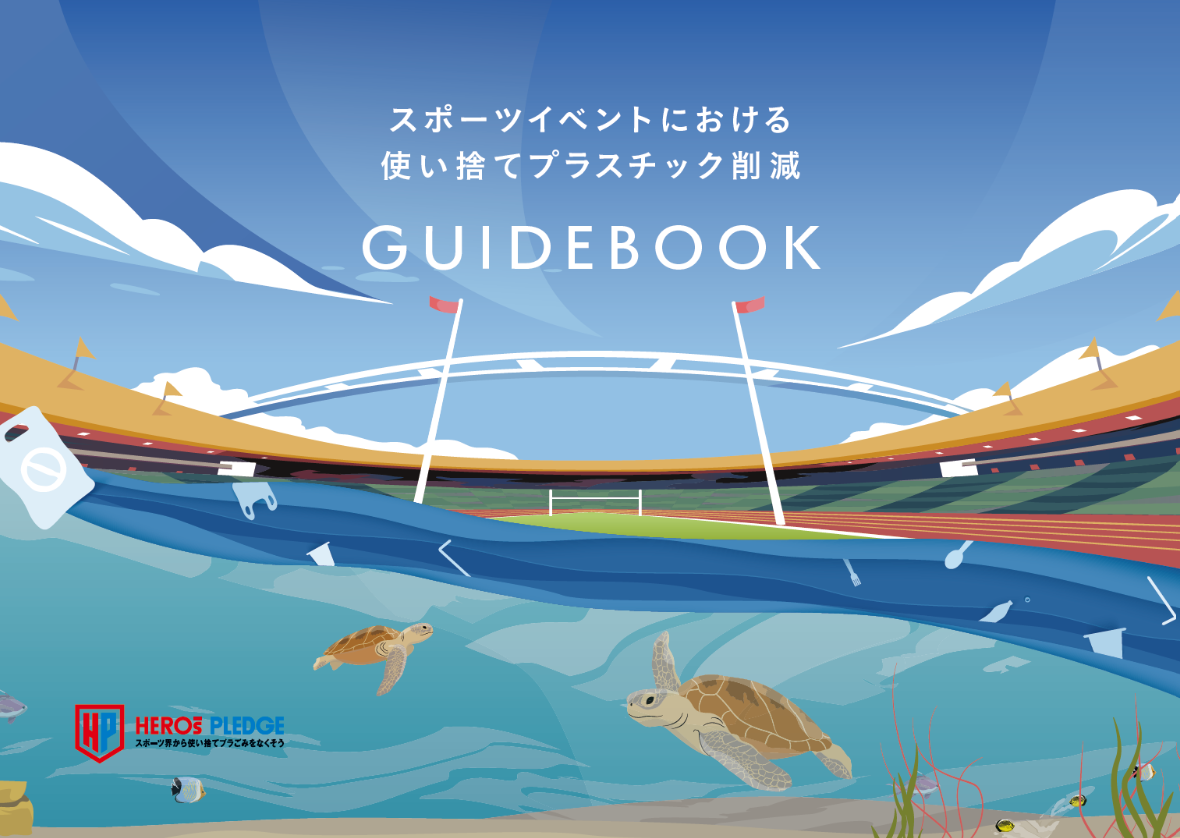
【担当者必読!】使い捨てプラスチック削減ガイドブック
使い捨てプラスチック削減の基本から、実際にアクションを起こすまでの実践的ステップをまとめたガイドブックを作成いたしました。 使い捨てプラスチック削減がチームにもたらすメリットやファンを巻き込み、組織を動かすコミュニケーシ...
記事を読む
日々のエコアクション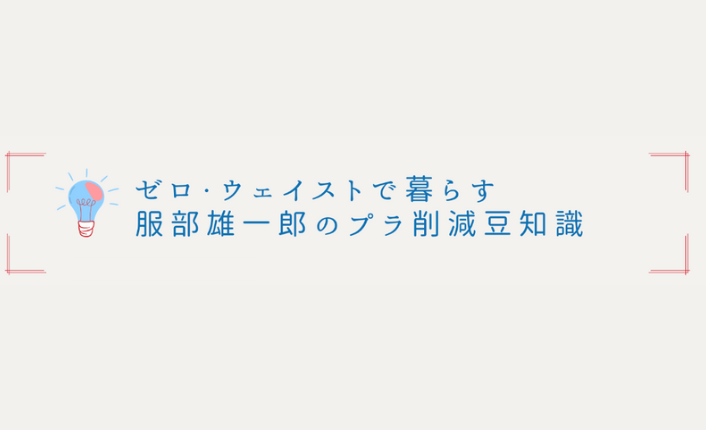
第16回『プラスチックはちゃんとリサイクルされているの?』
厳しい現実 各家庭で分別したプラスチックは、自治体が回収した後、さまざまな形でリサイクルされています。 ただ、残念ながらアルミ缶や古紙類のような「循環型のリサイクル」とは言いにくい現状です。 “ペットボトルが再びペットボ...
記事を読む
日々のエコアクション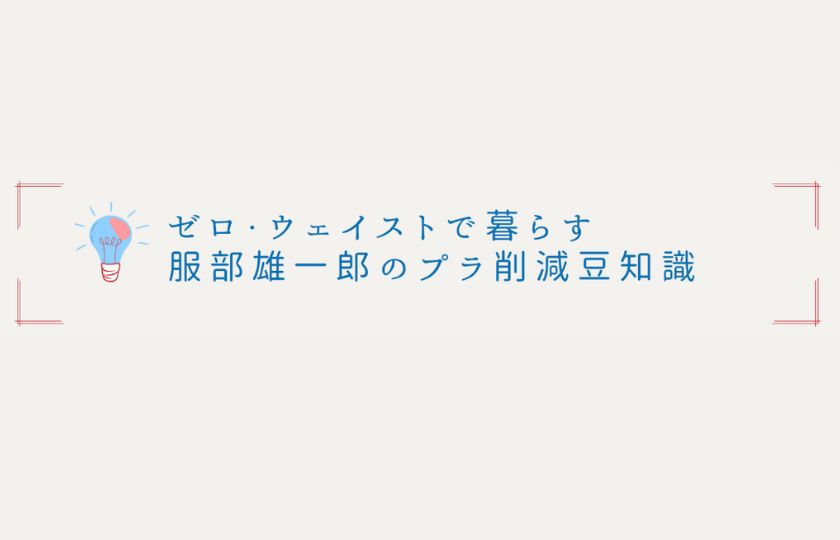
第15回『容器包装プラスチックの分け方・洗い方』
コンビニ弁当の正しい分別 コンビニ弁当のごみ、みなさんは自信をもって分別できていますか? 一口に「弁当のごみ」と言っても、まるごと全部が「容器包装プラスチック」にはなりません。 容器包装プラとなるのは、あくまでも食品や製...
記事を読む
日々のエコアクション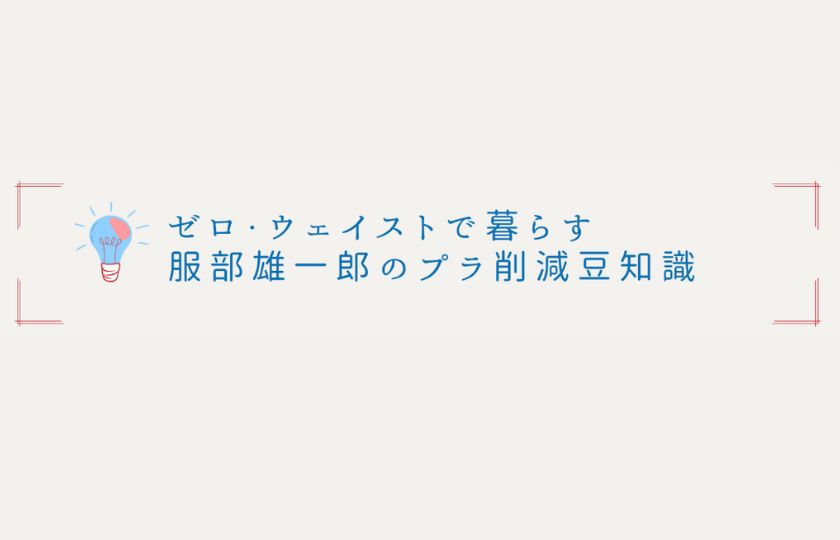
第13回『日本人は分別が得意』
日本の分別は世界トップクラス みなさんのお宅ではごみを何分別くらいに分けて出していますか? 日本は世界でもっとも細かくごみを分別している国のひとつと言われます。世界的に名高い「ゼロウェイストの町」徳島県の上勝町では驚異の...
記事を読む
日々のエコアクション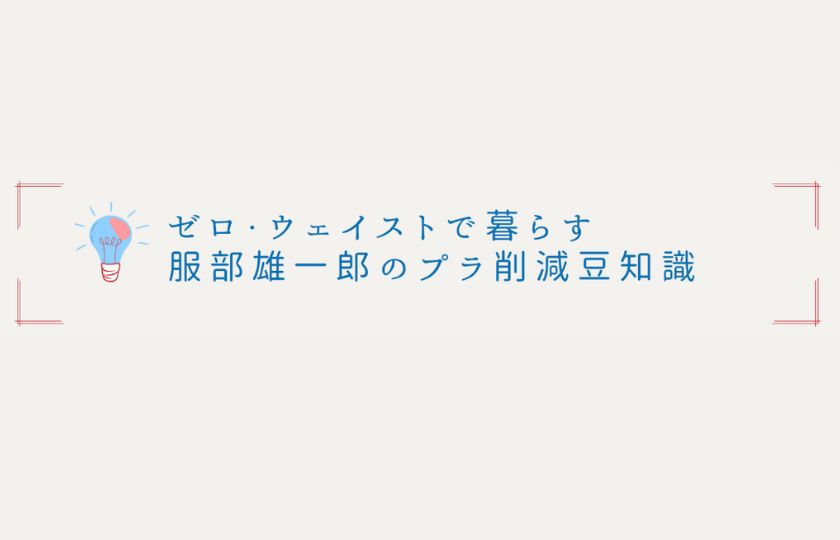
第12回『レジ袋有料化は間違っている!?』
有料化から5年 レジ袋有料化から、この夏で5年が経過しました。 この間、レジ袋の消費量は大幅に減り、マイバッグの持参も広く定着した感がありますが、今も「レジ袋有料化は間違っているのでは?」という批判が散見されます。 実際...
記事を読む
日々のエコアクション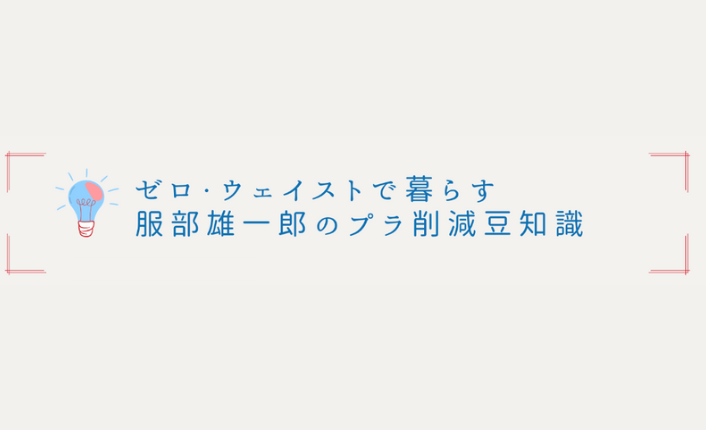
第11回『夏休みだからこそ、旅行のプラ減!』
アメニティは受け取らない 近年はサステナビリティの一環として、無料アメニティの提供を中止するホテルも増えています。 日本ではまだまだ各ホテルの自主性にまかされていますが、環境配慮の進む台湾では、一足先に2025年1月から...
記事を読む
日々のエコアクション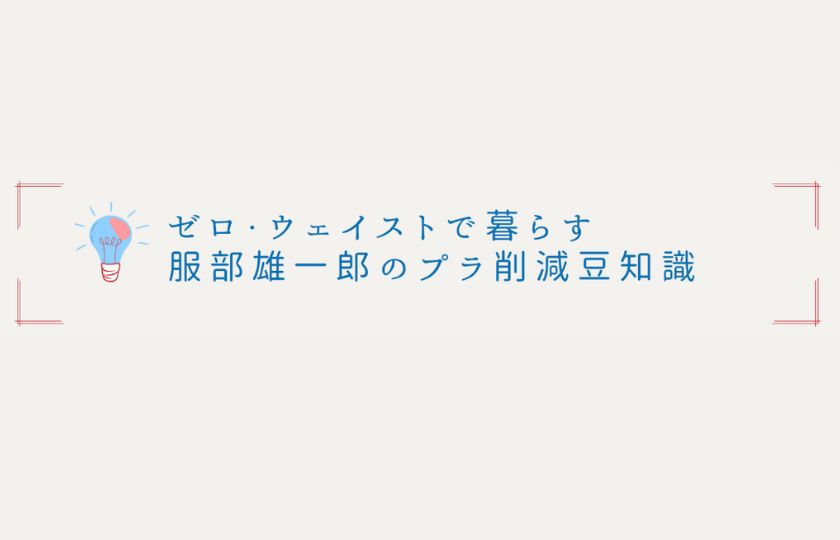
第10回『よく考えよう、無料配布のグッズ類』
ノベルティ配布は環境によくない 駅前などで目にする「ティッシュの無料配布」。 コロナ禍でだいぶ減ったようですが、実は海外ではあまり見られない日本特有の風習だと聞いたことはありますか? ティッシュに関わらず、チラシやマス...
記事を読む

