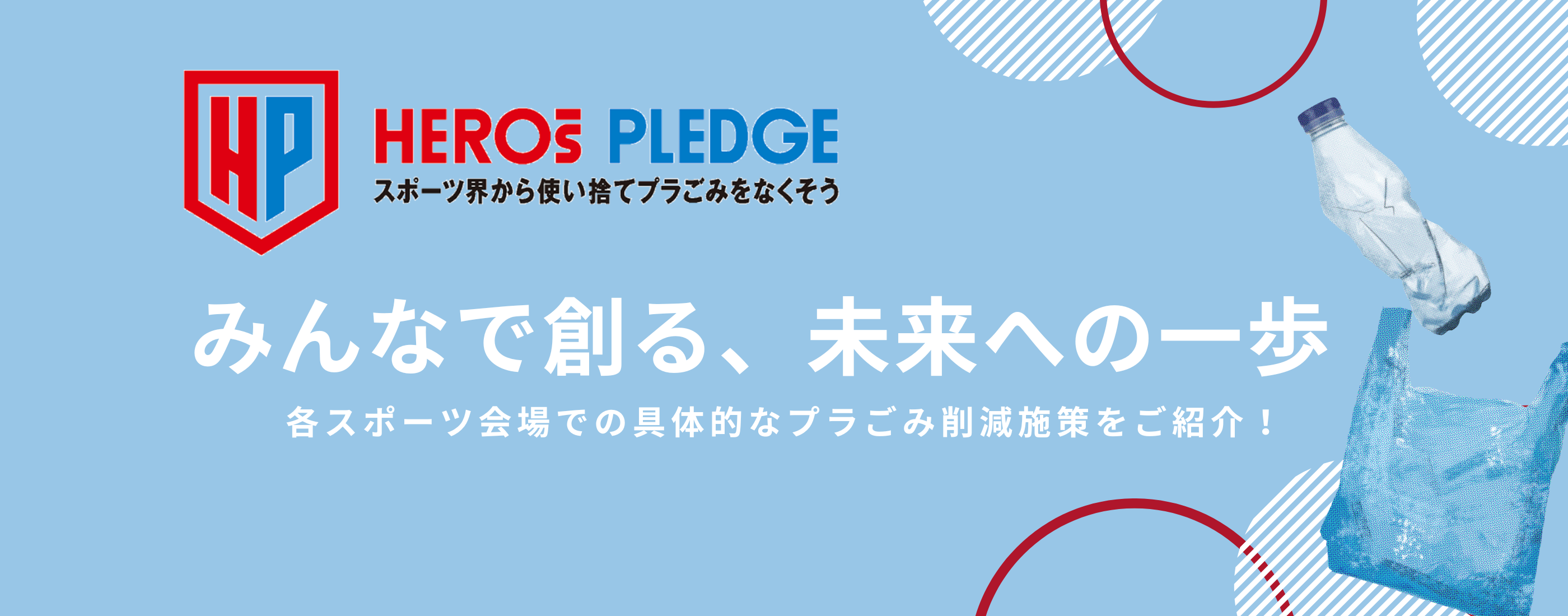
LEARNING CONTENTS
取り組み事例(その他)
国内トップレベル!
知って驚く、鈴鹿サーキットの環境配慮
2025年4月に鈴鹿サーキットで開催されたF1日本グランプリ。3日間の来場者数は、延べ26万6000人で、2009年以降の鈴鹿での日本GP開催としては最多の観客数となりました。そんな鈴鹿サーキットですが、実は環境配慮の面でも国内トップレベルの先進的な取り組みがされていることをご存知でしょうか?
「F1」と聞くと、「環境に悪そう…」と思う方もいるかもしれません。ですが、F1を開催するには、国際自動車連盟(FIA)が定める環境認証をクリアする必要があり、各開催地には高いレベルの環境配慮が求められています。鈴鹿サーキットでも、カーボンフットプリントの管理によるCO₂排出量の削減、使い捨てプラスチック削減の取り組みや、ごみの徹底的な分別やリサイクルなど、7年かけてさまざまな取り組みが行われてきました。こうした継続的な取り組みが評価され、鈴鹿サーキットはFIAの環境認証制度で最高ランクの「3つ星」を獲得。これにより、日本でF1を開催することができています。これらの活動を中心となって推進しているのが、ホンダの子会社であるホンダモビリティランドです。現地で取材してきました!
1.再生可能エネルギーの活用
鈴鹿サーキットの駐車場にはおよそ500台分の駐車枠にソーラーカーポートが設置され、鈴鹿サーキットの電力需要の一部を再生可能エネルギーで賄っています。F1開催時には、レーシングコースで使用する電力の45%を敷地内の太陽光発電で補うことに成功し、残りの電力もCO2フリーのグリーン電気を併用することで、安定供給とコスト削減を両立しています。
 |
2.ペットボトルゼロの実現と、徹底的な循環
場内レーシングコースエリアの自動販売機や店舗にはペットボトル商品が一切ありません。全て缶または瓶製品で販売していることに加え、無料の給水所を設置しマイボトルの利用を促すなど、ゼロプラスチックの取り組みをおこなっています。ただし、お客様の持ち込みによるペットボトルごみは出てしまうので、その対策として、回収したペットボトルを再びペットボトルとして再生する水平リサイクル「ボトル to ボトル」も導入しています。「ボトル to ボトル」の取り組みは、ホンダモビリティランド、コカ・コーラ ボトラーズジャパン、協栄J&T環境の3社連携により資源循環を実現し、質の高いペットボトルの再生が実現しています。
 |
 |
3.リターナブルカップの導入
場内で販売されているアルコール飲料も、一般的には使い捨てカップでの提供が主流ですが、鈴鹿サーキットでは「アルミ製リターナブルカップ」を導入。 UACJの協力により、何度も使用できる設計と高いデザイン性を両立したものを提供しています。再利用すると飲料を割引価格で購入できることや、その年限定デザインのカップを提供することで、使い捨て容器ごみの削減を実現しながらファンの満足度も高める取り組みとなっています。飲食店舗でも植物由来洗浄して繰り返し使えるの容器やカトラリーを使用することで使い捨てプラスチックを削減し、来場者には分別回収に協力してもらうことで、リサイクルの促進に取り組んでいます。
 |
 |
4.エコステーションの設置
F1開催中はレーシングカーのメンテナンスで出る廃材や、チーム関係者の食事から出た廃棄物を会場内で分別し、その後、会場外で分別しきれていないものを再度チェックする体制を組み、徹底的に分別しています。これには各国のチームの協力も必要になるので、第1チェック場所の「WASTE SORTING CENTER(廃棄物選別センター)」において、各チームから出た廃材がどんなものなのか、規定通り分別がされているのか、見える形で持ってきてもらうよう協力を呼びかけています。各国のチームに理解、協力してもらえるようになるには時間がかかったそうですが、今ではほとんどのチームが協力的に取り組んでくれているそうです。また各チームが拠点にしているハウスにはキッチンがあり、そこから出た食用油は会場内で来場者が利用するハンドソープに生まれ変わっているとのこと!
5.食品ロス対策:フードバンクとの連携
チーム関係者エリアで今年度出た未使用食材は約7.8トン。イベント最終日とその翌日に回収し、地域のフードバンクへ提供しています。この仕組みにより、食材ロスを減らすとともに、地域の福祉活動への貢献という社会的価値も創出しています。
 |
まとめ
他にも、イベント開催時のアクセス手段として、ツアーバス、パーク&ライド、ライドシェアといった多様な交通サービスを導入し、CO₂排出の削減に取り組むなど、新たなチャレンジを積極的に進めています。その「攻めの姿勢」こそが、鈴鹿サーキットのサステナビリティの真価であり、取り組みを進める動力であると言えるでしょう。ここまでご紹介した鈴鹿サーキットのサステナビリティ施策は、企業単独で完結するものではなく、自治体、地域、民間企業、といった多様なパートナーと手を取り合い、共創の姿勢で進められています。また「サステナ=コストがかかる」ではなく、「価値創出の機会」と捉え、未来志向での取り組みが進んでいます。
モータースポーツの枠を超えて環境に配慮されたこの取り組みがより多くの人に届くことで、他競技の大会運営やイベント運営など、さまざまな場面で活かされること、そして、私たち一人ひとりが「自分にできること」を考え、未来に向けてともに行動していくことが求められています。
その他の記事
日々のエコアクション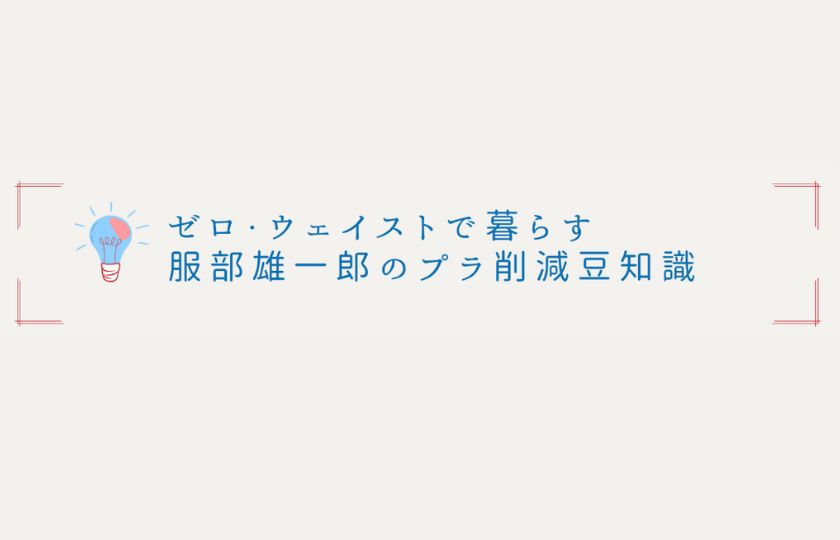
第17回『プラスチックは体に悪い!?』
プラスチックを「食べている」?? 数年前、「人は1週間にクレジットカード1枚分のマイクロプラスチックを食べている」という研究結果が広く報道され、社会に衝撃を与えました。 この数字は「さすがに盛りすぎだった」とも言われ、実...
記事を読む
取り組み事例(その他)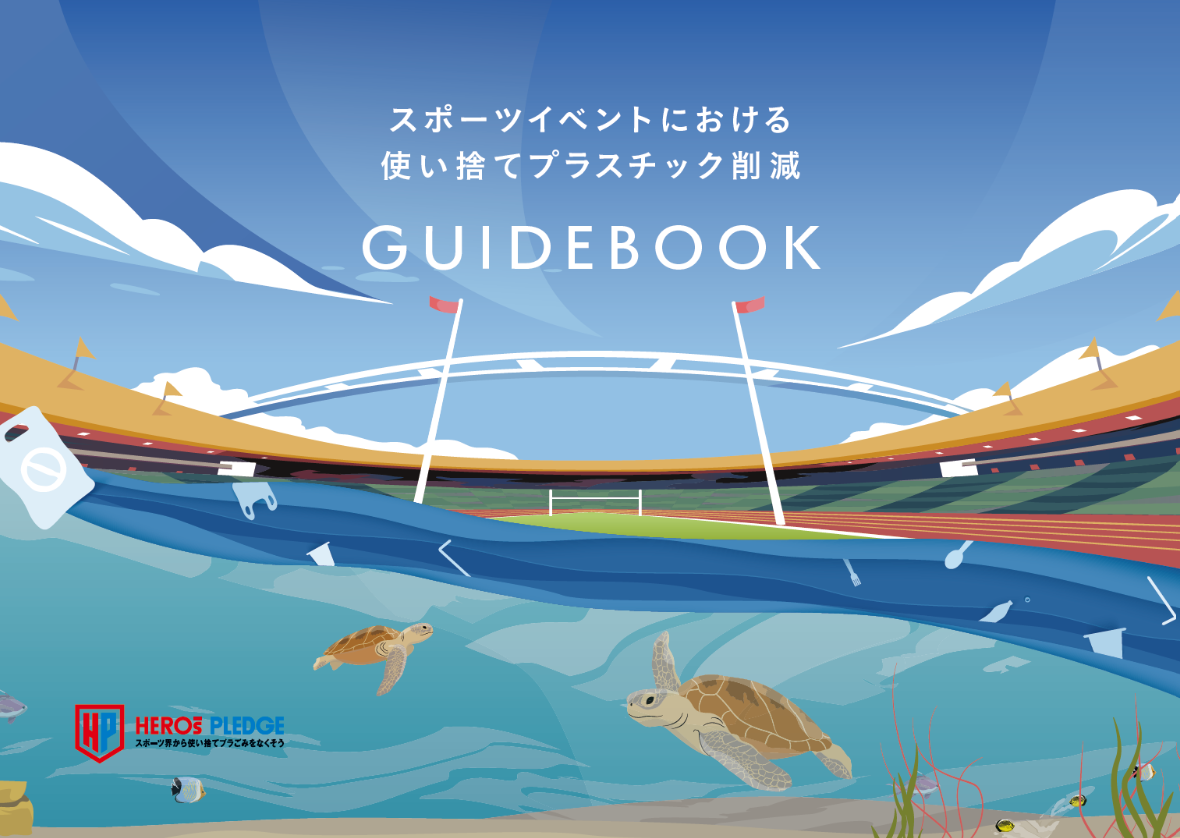
【担当者必読!】使い捨てプラスチック削減ガイドブック
使い捨てプラスチック削減の基本から、実際にアクションを起こすまでの実践的ステップをまとめたガイドブックを作成いたしました。 使い捨てプラスチック削減がチームにもたらすメリットやファンを巻き込み、組織を動かすコミュニケーシ...
記事を読む
日々のエコアクション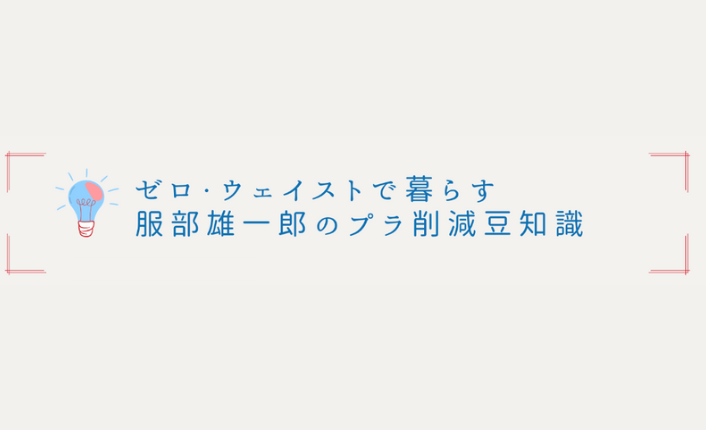
第16回『プラスチックはちゃんとリサイクルされているの?』
厳しい現実 各家庭で分別したプラスチックは、自治体が回収した後、さまざまな形でリサイクルされています。 ただ、残念ながらアルミ缶や古紙類のような「循環型のリサイクル」とは言いにくい現状です。 “ペットボトルが再びペットボ...
記事を読む
日々のエコアクション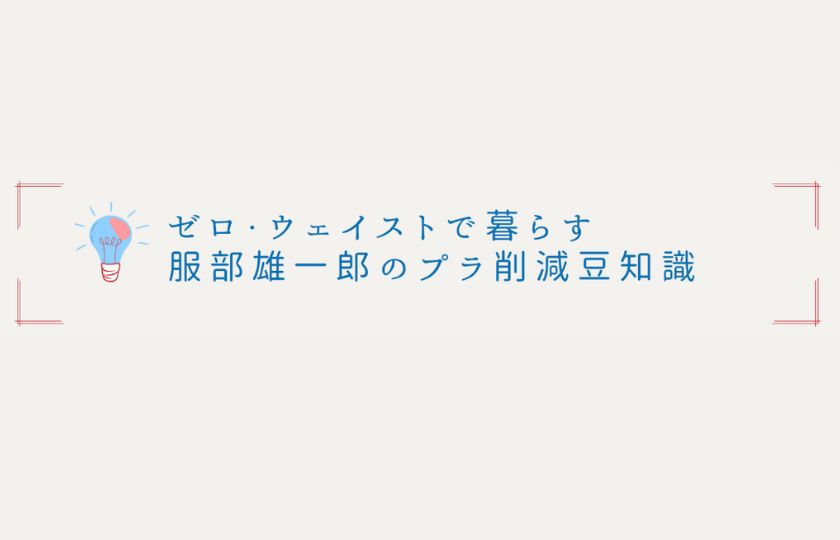
第15回『容器包装プラスチックの分け方・洗い方』
コンビニ弁当の正しい分別 コンビニ弁当のごみ、みなさんは自信をもって分別できていますか? 一口に「弁当のごみ」と言っても、まるごと全部が「容器包装プラスチック」にはなりません。 容器包装プラとなるのは、あくまでも食品や製...
記事を読む
日々のエコアクション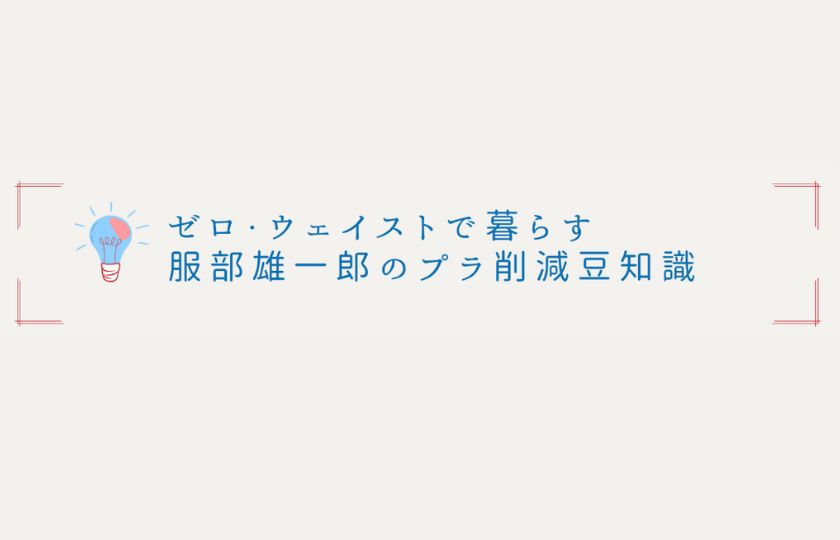
第14回『プラの分別、再確認!』
とてもややこしい「容器包装プラスチック」 プラスチックの分別、「実はあやふや…」だったりしませんか? 日本はごみの分別が自治体によってまったく異なるため、戸惑う方も多いことと思います。 まず、いちばん一般的な「容器包装プ...
記事を読む
日々のエコアクション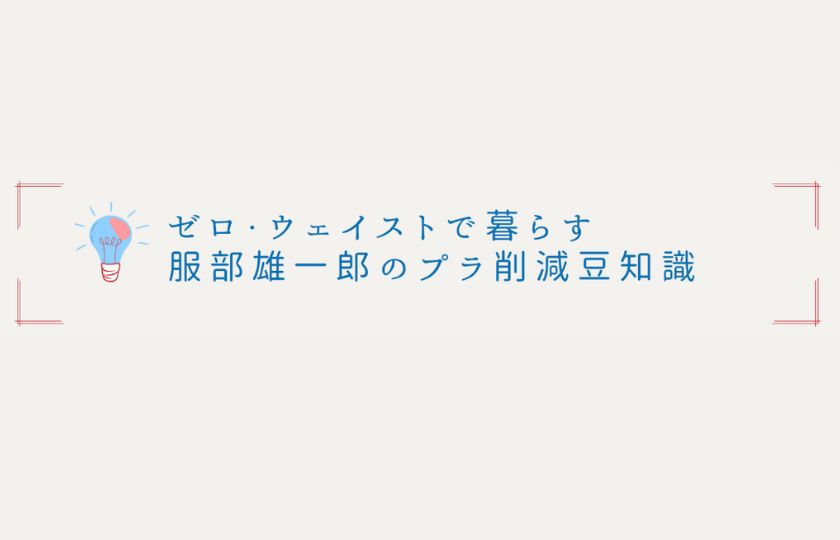
第13回『日本人は分別が得意』
日本の分別は世界トップクラス みなさんのお宅ではごみを何分別くらいに分けて出していますか? 日本は世界でもっとも細かくごみを分別している国のひとつと言われます。世界的に名高い「ゼロウェイストの町」徳島県の上勝町では驚異の...
記事を読む
日々のエコアクション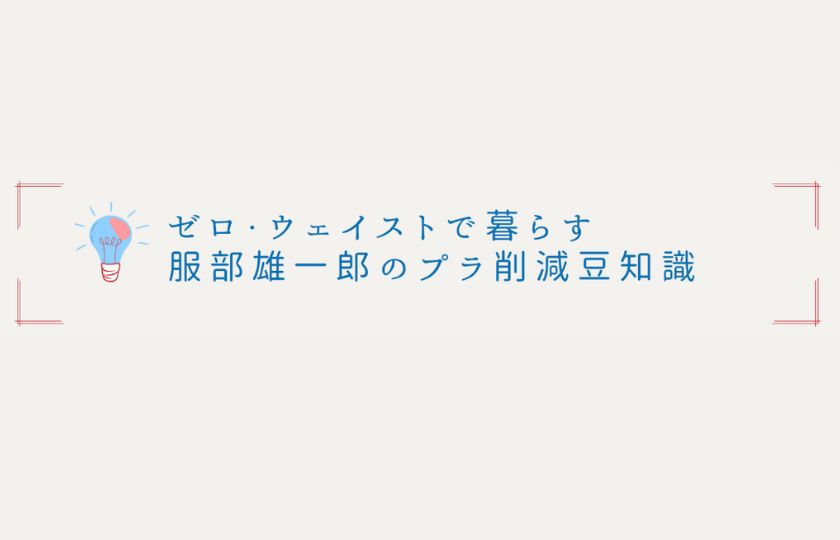
第12回『レジ袋有料化は間違っている!?』
有料化から5年 レジ袋有料化から、この夏で5年が経過しました。 この間、レジ袋の消費量は大幅に減り、マイバッグの持参も広く定着した感がありますが、今も「レジ袋有料化は間違っているのでは?」という批判が散見されます。 実際...
記事を読む
日々のエコアクション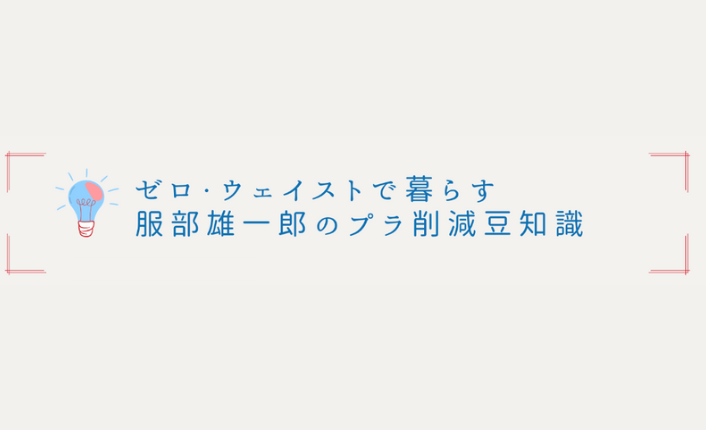
第11回『夏休みだからこそ、旅行のプラ減!』
アメニティは受け取らない 近年はサステナビリティの一環として、無料アメニティの提供を中止するホテルも増えています。 日本ではまだまだ各ホテルの自主性にまかされていますが、環境配慮の進む台湾では、一足先に2025年1月から...
記事を読む
